国土交通省が様々なプレイヤーと連携して推進する、日本全国の都市デジタルツイン実現プロジェクトProject PLATEAU(プラトー)は、「3D都市モデルの整備・活用促進に関する検討分科会」を改組し、「PLATEAUコンソーシアム」を設立しました。
本コンソーシアムには、アドバイザリーボードとワーキンググループが設置され、アドバイザリーボードの一員として、豊田特任教授が就任することをお知らせいたします。
今回の就任に関する詳細は、こちら(PLATEAU公式サイト)からご確認ください。

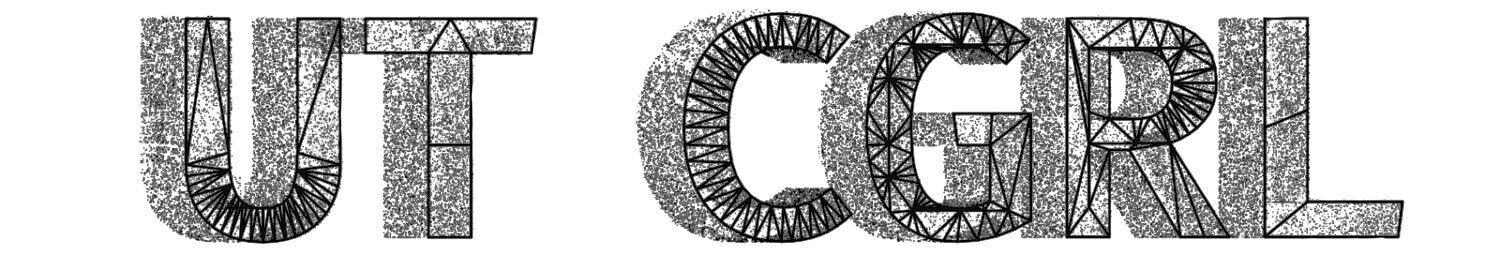

国土交通省が様々なプレイヤーと連携して推進する、日本全国の都市デジタルツイン実現プロジェクトProject PLATEAU(プラトー)は、「3D都市モデルの整備・活用促進に関する検討分科会」を改組し、「PLATEAUコンソーシアム」を設立しました。
本コンソーシアムには、アドバイザリーボードとワーキンググループが設置され、アドバイザリーボードの一員として、豊田特任教授が就任することをお知らせいたします。
今回の就任に関する詳細は、こちら(PLATEAU公式サイト)からご確認ください。
